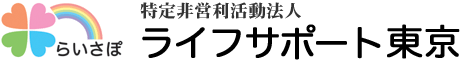知的障がいの事例
モデルケース N郎さんと母F美さんの場合
この事例は複数の事例を組み合わせるなどして構成したものであり、実際の事例とは名称、年齢、地名等は異なります。
N郎さん(42歳)は、幼い頃に知的障がいの診断を受け、母親のF美さん(73歳)と二人暮らし。特別支援学校を卒業したあと、就労施設に通っています。
わかりやすい指示をもらえば軽作業などはできますが、複雑な作業や自分から自発的に行動することは難しく、ずっとF美さんがN郎さんの生活を支えてきました。
しかし、最近N郎さんの世話や家事が負担になってきたF美さんは、自分の老後と、自分が亡くなった後のN郎さんの生活が不安になり、最寄りの社会福祉協議会に相談に行きました。
社会福祉協議会から、F美さんとN郎さんの将来の不安について、二人それぞれ「成年後見制度」が利用できることを教えてもらいました。特にN郎さんはまだ若いので、これからの長い人生を継続して支援してもらえるよう、「法人後見」を行っているライフサポート東京を紹介してもらいました。
らいさぽの対応
F美さんはライフサポート東京の頼佐保太さんと面談し、今後の生活について相談をしました。
その結果、F美さん自身は、将来の要介護生活や死後の手続きに備えて「任意後見契約」と「生前・死後事務委任契約」を、ライフサポート東京と結ぶことにしました。
またN郎さんへは、「法定後見」を利用して速やかにN郎さんに「後見人等」を選任してもらい、F美さんが元気なうちに積極的に関わりながら、N郎さんと「後見人等」との間で信頼関係を育んでもらうことにしました。
2ヶ月後、ライフサポート東京をN郎さんの「保佐人」とする審判が下り、担当者となった頼佐保太さんは、あらためてN郎さんと母F美さんと、今後の生活について話し合いました。F美さんは、「自宅でN郎さんの世話を続けるのはもはや難しい、N郎さんに知的障がい者用のグループホームへ入所してもらいたい」という希望を述べました。最初は「お母さんと一緒がいい」と抵抗を示したN郎さんでしたが、F美さんの体調を理解して、最終的には、グループホーム入所に同意しました。
頼佐保太さんは、早速グループホームへの入所手続きをとり、N郎さんはホームへ引っ越しました。慣れるまでは、F美さんとしばしば外食したり、週末だけ自宅へ外泊したりして、少しずつホームの生活に慣れていきました。
その後
ホームでの生活に慣れ、N郎さんの自宅への外泊は月に1度。F美さん自身もライフサポート東京の支援を受け、自分のこれからに関する心配が減り、月に1度、N郎さんのために食事を作って待つのが大きな楽しみになっています。N郎さんは、頼佐保太さんの名前も憶えました。
F美さんは、グループホームで生活を始めてからN郎さんのできることが増えて一回り成長したことを感じ、これなら将来自分が先に亡くなっても、頼佐保太さんをはじめ様々な支援者のサポートを受け、N郎さんが生活していけるだろうとホッとしています。