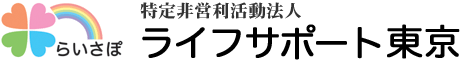遺言書作成の事例
モデルケース A代さんの場合
この事例は複数の事例を組み合わせるなどして構成したものであり、実際の事例とは名称、年齢、地名等は異なります。
A代さん(68歳)は15年前に夫を亡くし、都内の一戸建てで一人暮らしをしています。
子供は二人、長男は夫の工場を継ぎ、長女は横浜へ嫁ぎ、それぞれ家庭を持って生活しています。
夫を亡くした時、相続財産に差ができてしまい、遺産分割協議の合意に時間がかかったうえ、子供たちの間に溝ができたような気がしていて、A代さんは自分が亡くなった後、さらに子供たちの溝が深まるのではと心配していました。
A代さんが友人に相談したところ、「うちは夫が公正証書で遺言を作っといてくれて、亡くなった時モメなかったわよ。私も作ってあるの。A代さんも遺言を作ったら?」と勧められました。A代さんが「遺言なんてどう書くのか分からない」と言うと、友人の遺言書作成を支援したライフサポート東京を紹介してくれました。
らいさぽの対応
ライフサポート東京へ電話したところ、後日、事務局長と、遺言書作成を支援してくれる行政書士が、A代さんの自宅を訪問してくれました。遺言の種類や作成方法について丁寧に説明があり、A代さんも「公正証書遺言」を作成することにしました。作成費用はかかりますが、法律のプロである「公証人」が有効な証明力のある書面を作成してくれて信頼度が高く、自筆証書遺言よりモメる要素が減るとのことだったからです。
行政書士は、A代さんと何度も打合せ、A代さんの財産状況に加えて、子供たちへの想いや希望を詳しく聞き取りました。最初はどんな遺言を書いたらよいのかと不安だったA代さんですが、何度も行政書士と話すうちに、次第に状況が整理され、気持ちが定まってきました。
A代さんは、夫の時の遺産分割協議の差に配慮しながら、長女に自宅を、長男に工場の株式をそれぞれ相続させ、預貯金を長男に少し多めに配分する遺言を作ることにしました。また、子供たちが相続手続きに時間と手間を取られるのは負担になるだろうと思い、「遺言執行者」にライフサポート東京を指定し、遺言を確実に実行してもらうようにしました。なお遺言には「附言事項」を加え、財産をこのように分配した理由と、二人きりの兄妹なのだから仲良くしてほしいという、子供たちに向けたメッセージを託しました。
行政書士は、A代さんの希望をくみ取った文案を作成し、遺言作成に必要な戸籍謄本等の証書類の収集や、公証役場との日程の調整等をしました。
作成日当日は、A代さんの公証役場訪問に行政書士も同行。証人2名が立会い、A代さんの公正証書遺言が完成し、原本は公証役場が保管、A代さんは正本と謄本を受領し、後日「遺言執行者」となるライフサポート東京に正本を預けました。
その後
A代さんは、今回遺言を作成したことで、心配事がひとつ減り楽になりました。一人で心配して思い悩むより、専門家に相談することでより良い解決方法に近づくことができると感じました。